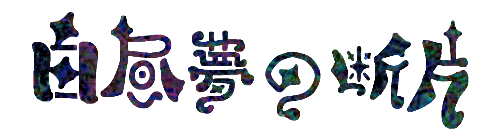それきりそれを見ることはもうない、というのが普通なはずなのに。それなのに、喫茶店を出て友人を合流してからもあの赤い影がチラチラとつきまとっているような気がしてしょうがなかった。ガラスの映り込み、噴水の水の反射、人混みの中に混ざる赤い髪。本当にそこに存在していたのか定かではない。だけど、どこかにあのときの、あの人の気配がしているように感じられてしょうがなかった。
それがあの日だけならまだよかった。それの気配は次の日もその次の日も私につきまとってきた。まるで私の跡をつけてきたかのように生活圏にも存在を感じるようになった。
自宅のそばの消えかけの街灯の下。明滅に合わせてあのときの彼がそこに現れては消えた。
またあるときは、4階にある私の部屋を目指して階段を登っていると人影とすれ違った。で暗くてはっきりとした姿は見えなかったが、あれはたしかに、赤くて長い髪をしていた。この家の住民にそんなやつはいなかったはず。恐ろしいのに、なのについ、目が彼を追いかけてしまう。きっと私こそ狂っているのだろう。そもそも初めて見たときにそれが実在の人物だったかすらわからない。
実在するかも不確かな恐ろしい存在。なのに、それの気配を感じるたびに胸が高鳴る。怯えからくるものだけでない。ときめきに似た気分の高揚。それと目が合う瞬間を楽しみにしていたのはいつから? もしかしたらはじめから?
本能的恐怖とそれに反したある種の恋慕のような感情と、その感情への嫌悪。滅茶苦茶な思考で精一杯自分の感情を分析する。おかしな話だ。自分の見た幻覚かもしれない存在にこんなに狂っているなんて。
今日も明日も、いつもの街灯の下に彼がいることを期待しながら帰宅する。はじめこそいたりいなかったりだったが、いまでは毎日そこに存在を感じられる。そこかしこであの人の気配を感じるがここだけは自分の妄想なんかじゃなく実在していると思えた。淀んだ赤と緑の目。瞬きをしてじっとりとした眼差しでこちらを見つめる目。見つめすぎているとそのまま魅入られてしまいそうだから目を合わせるのは数秒だけ。私が街灯のそばを通り過ぎてもそれは微動だにせずそこにいるだけ。
ああ!もしかしたら!あの人も私のことが気になっているのかも! ……なんて。キチガイじみた考えまで浮かぶようになってしまった。
けれども、彼が非実在でなく実在で、私の跡をつけていつもここにいるとするならば、わざわざそうするくらいに私に関心があるということではないのか? もういっそ、あの人に私から話しかけてみようか? もしかしたらあの人の声が聞けるかもしれない。あのおぞましくも美しい存在はどんな声色をしているのだろう? 明日にでも声をかけようか。だけど、第一声はなんて? 何から言えばいい? いきなり話しかけて不審がられないだろうか? そのせいでもう会えなくなってしまったらどうしよう? ……心苦しいが今の状態を維持するべきなのかもしれない。
そんなある日、ついにあの人から声をかけられてしまった。
「ねえ、あんた……」
女性にしては低く男性にしては高めな不思議な声、抑揚は少なくどこかねっとりと耳に残る声。突然のことに動揺してもっと聞きたかったのに、言葉の途中で足早に立ち去ってしまったことを人生で一番後悔した。
声を聞いてからは家でも外でも彼の存在を感じられるようになった。鏡の中にも窓ガラスの中にも、カーテンの向こう側にも。
それだけじゃない。耳元で常に囁かれているような感覚も増えた。何を言っているのかは聞き取れない。だけどきっとこれは、あの日言いかけた言葉に違いない。
いつかそれを聞き取れる日が来るのだろうか? きっと遠くないうちに来ると私は信じている。
なのに、こんな、ひどい。違う。思っていたのはこんな結末じゃない。どうしてこんな、なぜ? なにがどうしてこんなことに?
いつものように街灯のあの人を数秒見つめて帰ったある日。窓の外にいるような気がして外をぼんやり見ていた。一瞬赤いものが見えて本当にいたのかとドキリとしたが室内の明かりの映り込みがそう見えただけで肩を落とした。
その数秒あと。刹那の瞬間。だけど私にとっては永遠のような時間。赤いあの人が、いつもの彼が、窓の外に。逆さまで。赤い髪がバサバサと揺れ落ちていく。落ちていく。どこまでも。そのときのあの人の顔は、初めて見たときと変わらず目をそらせない気味が悪いほどの笑みで。
いけない、こんなことを考えている場合じゃない。あの人は何をした? これは投身自殺じゃあないのか? 冷静な思考を取り戻した途端、なんとも形容詞がたい音が地上でした。
慌ててベランダへ出て下を見る。そこには変わり果てたあの人の姿だけがあった。彼の片目と同じ淀んだ暗い赤に塗れてどこの部位かわからない臓物や脳漿をぶちまけた無残な姿。
吐き気がこみ上げてくる。死んだ人間を見たことがないわけじゃない。だけどそれは病気や老衰で穏やかに最後を迎えた姿だけで。こんな、目の前でさっきまで生きていたはずの人間が、こうなってしまうところなんて。見たこともないし見ることもないと思っていたのに。
受け入れがたい現実と衝撃にうずくまる。ここで嘔吐してしまえば彼を否定するようでそれも嫌だった。だけど嗚咽が止まない。喉奥に酸っぱいものがこみ上げてくる。吐きたいのに吐けない苦しみ。
ただ今この瞬間、この苦しみから逃れたい。そしてふと気づく。彼と同じになればいいんじゃないか! どうしてこんな簡単なことに気が付かなかったのだろう!
ああ、いまそばに行くから。待っていて。
朝焼けの中に血溜まり一つ。死体が一つ。