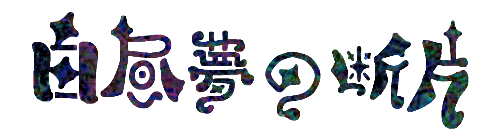さつきと暮らすようになって、すべてがうまく行っていると思っていた。
外を歩けばすべてが鮮やかで新鮮に思えて。幾百も眺めてきた季節の移り変わりだってまったく新しいことのようにさえ感じた。あの子が隣にいるだけで、笑ってくれているだけで、こんなにも世界は美しい。ずっと、ずぅっと、こんな日々が続けばいいなと思っていた。
なのに最近、さつきがよそよそしい。避けられているというか距離を置かれてるというか、とにかくそんな感じがする。
まず第一に、一緒に寝てくれなくなった。厳密には同じベッドで寝ているのだけれど間隔を空けて私に背を向けて眠るようになった。
「さすがにもう一人で寝ないと恥ずかしいし狭いから」
と、そこらのソファで眠ろうとしていたけれど、なんとか説得した。だめじゃない、育ち盛りなんだからちゃんとした所で寝ないと。それに恥ずかしいことなんてまったくないし私のベッドは二人寝たって余裕があるくらいの広さなのに。
背中を向けて眠るさつきにちょっかいかけてみるけれども何も反応がなくて寂しい。
次に、めったに手を繋いでくれなくなった。前は出かけるときはほとんど手を繋いで横並びで歩いてくれたのに、最近はすたすたと前を歩いていく。もちろん私を置いていくほどのペースではないけれど。
並列から直列。これもまた寂しい。
そして最後に、よく目をそらすようになった。そう、最近目を合わせてくれることが少ない。昔は見つめると戸惑いながらも真っ直ぐに私に視線を返してくれたのに。今は、わかりやすく顔をそらしたりうつむいたり。何かを恐れているのか後ろめたいのか、そんなくらいに。
読書をしているときにふと顔を上げて、さつきと目が合うと少しぎこちなく微笑み返してくれるそんな瞬間が好きだったから悲しい。
他にも一緒にお風呂に入らなくなったとか夜歩きに付き合ってくれなくなったとか色々あるけれど、とにかく、さつきと距離が遠くなったような気がして私は寂しかった。
……これはあのとき、私が吸血鬼だと明かしてしまったから?それとも他に何かさつきに嫌われるようなことをしてしまった?
わからない。よそよそしくなったのは明確にあの日を境にというわけではないし、いったい何が原因なのか想像もつかない。
いっそ直接、さつきに聞いてしまおうか。ああ、そうしよう。いつまでも悩んでいるよりそれがいい。それで嫌われてしまうくらいならきっともう嫌われているもの。ふふ、さつきになら嫌われて生涯をかけて憎まれるのも悪くないかな。ああもう、別にまだ嫌われたって決まったわけじゃないの
に。
さて、そういうわけで私は、書斎机に向かって本を読みながら何か書き写しているさつきの後ろから声をかけた。
「お勉強?わからないところがあれば教えるよ」
「!?……だ、大丈夫」
「そう?……えらいえらい」
と、いつもの癖でさつきの頭をなでようとするとサッと振り向かれてしまい私の手は行き場をなくす。
……避けられてしまった。
しょげていたって仕方がない。早く本題を切り出さないと。
「あのね、」
緊張した面持ちでこちらを見ているさつきに問いかける。
「な、なんだよ……」
「最近私のこと避けてる?」
「そんなことっ……な、い」
最後のほうは消え入りそうな声だった。どうして?それは認めたくないことなのかな。悲しいことに私には人の心の機微がいまだによくわからない。さつきがどのように感じてそのように答えるのか、わからない。
だから私にできることは、私が感じていることを率直に伝えるだけ。
「怒ってるわけじゃないよ」
「本当に?」
「怒らないよ。ただ少し悲しいだけ」
「……やっぱり怒ってない?」
――さつきは昔から私が怒ってないか心配していたっけ。私が怒ったことなんてないのにね。
「ないってば。……教えて欲しいだけ、どうして私のことを避けるのか。何かさつきが嫌なことしてしまったかな?」
「……別に」
「それならどうして」
「……うぅん」
困ったようにうなるさつき。そんなに言いにくい理由なのかな。となるともしかして、あの日がきっかけ?
「私が吸血鬼だから?」
「っ……そ、そういうわけじゃ!」
明らかに動揺した様子。本当にこれが原因なのかもしれない。
「信じてもらえなくても仕方ないよね、でもね、私の口先が嘘を吐いても私の心音は嘘を吐かないよ」
そう言ってギュッと心臓を押し付けるようにさつきを抱き寄せる。おかしなものだ、何千年も生きていながら上手なことなんて言えず結局安直な触れ合いでしか示せないなんて。
「わ、わ……!?だ、だから咲々牙は距離が近すぎるんだって……!」
腕の中のさつきがジタバタと暴れる。……私の思いは拒絶されてしまったみたい。そうなれば仕方がない、アレしかない。信じてもらう方法、もう他にわからないもの。
遠慮がちな抵抗を続けるさつきを解放して壁際の本棚を探る。ええと、あれはこのへんの……あの表紙の、あっこれだ。
いきなり本棚を漁りだした私を見て疑問符を浮かべているさつきに取り出した大きく分厚い本を手渡す。
「……?これは?」
「中を開いて」
言われるままにさつきが本を開くと中には銀の弾丸とピストル。世の中には変わった物品があるもので。
中身を見てなお戸惑うさつきに答える。
「あのね、それをあげる。さつきがもし私のことを嫌いになったり怖いと感じたりしたらいつでもそれを使って」
「へ!?いや、そうじゃなくて……!」
「?」
「だ、だから、そういうわけじゃないんだって……!」
「じゃあどういうこと?」
そうじゃない、というのは「私が吸血鬼だから」ということについてなのか。ううん?私が深刻に受け止めすぎていた?
「……夢を見たんだ」
渡した本のような何かをひとまず机に置いたさつきが答える。
「夢?」
「……変な夢」
「それが私に関係するの?」
こくこくと首を縦に振るさつき。どういう夢だろう、やっぱり私がさつきを殺してしまうとかもっと酷いことをするとかそういう……?
「夢でさつきに酷いことしちゃったかな?」
「そ、そうじゃない……!むしろ逆、のような……」
「なるほど?じゃあ私は夢でさつきに殺されちゃったりしたのかな」
「それも違う……!」
難しい。謎掛けでもしているような気分だ。そろそろ答えを教えて欲しい。
「それならなあに?いい加減教えてほしいなあ」
「い、言わないとだめ……?」
「だめ、教えて」
ここまでくると本来の目的を忘れるくらい気になってくる。ここで聞かなかったら夜も眠れなくなってしまいそう。
「…………えっちな夢」
うつむき赤面しながら答えるさつき。
……想定外の回答に吹き出してしまった。あっ、そういうのなんだ。
「わ、笑い事じゃない……!」
「ごめんごめん、だってもっと殺伐とした感じのことかと思っていたから」
「こんな恥ずかしいこと言わせて笑うのひどい!」
「恥ずかしくないってば。そうだねえ、さつきだってもう子供じゃないもんね」
そういうことか。大人になるにつれて親離れするようなものか私を異性のように認識しているのか、どちらかはさておきだいたいそういうこと、なのかな。最近目を合わせてくれないのも見つめ合うと思い出してしまうから、とかそういったところか。
「ちなみに、どういうことしていたの?」
「っ!そんなの言えるわけないだろ……!」
うーん残念。さすがにこれは教えてくれなさそう。さつきの言う「えっちなこと」がどの程度のものを指しているのかはわからないけれど、ひとまず嫌われてはいなさそうでよかった。
それはさておき、避けられていた原因が分かった喜びで思わずさつきを抱きしめてしまう。
「そういうのはだめ、だって……!」
やんわりと引き剥がされてしまった。
「私は別に構わないよ」
さつきはブンブンと首を横に振る。そんなに拒絶されると少し悲しくなる。
「さつきは私のこと嫌い?」
真っ直ぐにさつきを見つめて問う。顔をそらせないようにそっと両肩を掴んで。
「き、嫌いじゃない……。どちらかというとす、き……」
消えてしまいそうな声色。
「好きだけど抱きしめたりするのはだめなの?」
「なんていうか、よ、よくないっ!普通は家族とはこういう距離感で触れ合わないと思うっ……!」
そっかあ。ううん、そういうものなのかあ。「家族」じゃだめ、ということなのかな。
「……私はね、さつきの家族にも恋人にも、すべてになりたいと思っているよ」
まるで告白みたい?そうかもしれない。私は「家族」以外でもさつきとずっと一緒にいられて触れ合って存在を確かめられるなら何でもいい。とにかく私は出会ったときからずっとさつきのことが「好き」だから。それだけは天地がひっくり返ろうとも覆ることはないだろう。
「っ〜〜!」
顔を真っ赤にしたさつきは私の手を振り払いそのまま走り去ってしまった。
「の、喉が渇いたから水!水飲んでくる……!」
少し離れてから声がする。完全に逃げられてしまった。まあいい。……これからのさつきとの関係をどうしていくか少し考えないと。
置き去りにされた私と机のピストルを窓の外の痩せた三日月だけが見ていた。