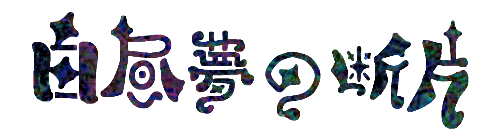半分の月が窓から顔を覗かせる頃、涼しい風がカーテンをゆらし吹き抜けていく。そんな景色を眺めて艷やかな黒髪のあの人は微笑んだ。
あの日、両親を亡くしてからオレはあの人――咲々牙と一緒に暮らしている。
遺体は見ないほうがいい、とすぐにあの人が埋葬した。思い出の残るこの家にいるのもつらいからとあの人の家で暮らすことになった。
どうして見ず知らずであの日のショックでろくに口もきけなかったオレにこんなに親切にしてくれるのか、想像もつかない。けど何もかも失ったオレはそれに甘えることしかできなかった。
あの人と暮らすうちにわかってきたことがある。
ささげは「咲々牙」という字を書くらしい。
……なんだか不思議な字だけどこの人らしい感じがする。
咲々牙はいい匂いがする。
季節に薫る花のような自然でどこか懐かしいような香りがする。
そばにいるとなんとなく気分が落ち着く。
咲々牙は食事を摂らない。
食事をしているところを見たことがない。食べないのか聞いてみたら
「そういう生き物だからね。こわがらせてしまったかな?ごめんね」
と言っていた。ううん、よくわからない。
咲々牙は日の光が苦手だ。
好き好んで日中外に出ることはない。雪のように白い肌をしているからきっと肌が弱いんだ。
それなのにときどき行く買い出しには「一人だと心配だから」とついてきてくれる、日傘を差して。
咲々牙は雨が嫌いだ。
雨の日にはつまらなそうな顔をして窓の外を眺めていた。この日は買い出しに行くのも別の日のほうがいいと止められた。
オレも雨の日は好きじゃない。なんとなく陰鬱な気分に なるし靴がびちゃびちゃになる。……咲々牙の気持ちがわかるような気がする。
咲々牙は体温が低い。
よくオレの体に触れては「さつきはあたたかいね」と言っている。咲々牙は楽しそうだけどオレは少し恥ずかしい。
咲々牙は夜が好きだ。
しばしば夜にカーテンを開けて月を眺めている。……もしかしたらこの人は月の妖精とかなのかもしれない。ある日突然月に帰るとか言い出したらどうしよう。
咲々牙は花が好きだ。
家の花瓶に花を生けると嬉しそうな顔をする。
夜、一緒に散歩しようと誘われたことがある。ランタンに火を灯し、薄闇の中、手を取られ二人で歩いた。
きれいな白い花が咲いているのを見た。これが見せたかったんだと言って咲々牙は笑った。
咲々牙は心配性だ。
オレが一人で外に行くことにいい顔をしない。大抵の場合一緒に行こうとする。日光は苦手なはずなのに日傘を差してでも。
もう一人でどこかに行くのが心配な歳でもないのに。……たしかに急に不安になるときもあるけど。
咲々牙は冗談をを言うのが好きだ。
月の中に住んでいる人たちがいるとかもう1000年以上生きてるとか突拍子もないことを言う。
だいたいは嘘だと思うけどまるでそれが本当みたいな調子で言うからそんな気がしてきてしまう。
咲々牙はオレのことをくすぐるのが好きだ。
なんだか恥ずかしいしくすぐったいから少し困る。でもまあ、すぐにやめてくれるからまあ、いい。
どうしてくすぐってくるのか聞いてみると「さつきの笑ってる顔が見たいから」と言っていた。
ますます恥ずかしい気がした。
咲々牙は、もしかしたら吸血鬼なんじゃないかと思う。
日光が苦手、雨が苦手、冷たい体、普通の食事をしない。これらのことから導かれる答え。日光と雨だけで考えるのは早計かもしれない。だけど食事をしないのは変だ。本人が言うように少なくとも「ヒトではないナニカ」なことに違いはないだろう。
……昔、太陽を恐れるものはよくないものだと聞いた覚えがある。それなら咲々牙はよくないもの?こんなにオレによくしてくれるのに?
だいたい吸血鬼だとしてもオレのことを食べたりしてないのはおかしい。あの人はいつもニコニコしてオレに触れるばっかりだ。吸血鬼はヒトを食べてしまったりとか一滴残らず血を吸い尽くしてしまったり、そういうものなんじゃないのか?
……わからない。でも、もしも、もしあの日にオレの家族を襲ったのが咲々牙で、オレのことはもっと美味しくなってから食べるつもりだったりしたら……。
そもそも考えてみると不審な点はたくさんある。両親の遺体をオレに見せなかったこと、なぜあの日そんなちょうどよくオレの家のそばを通りかかったのか、なぜわざわざ見ず知らずの相手の面倒事なんかに関わろうとしたのか、考え出すと何もかもが不可解。
……きっと咲々牙が優しすぎるから。優しすぎるからわからないんだ。こんなにいろいろしてもらってるのに馬鹿げた疑いをかける自分が恥ずかしくなる。
「どうかしたのかい?さっきからずっと何か考えた顔して」
安楽椅子に腰掛けて窓の外を眺めていた咲々牙がふいにこちらを向いて問いかけてくる。
「ええと……、咲々牙のことを考えてた」
「本当?うれしいな」
そう言うと椅子から立ち上がり、ずいと近づきオレの顔を覗き込む。
「ね、私のなにを考えていたのかな。教えて?」
赤い瞳に射すくめられる。この眼に見つめられると嘘がつけなくなる。だから適当に誤魔化せばいいはずのものを率直に答えてしまう。
「咲々牙が、本当は吸血鬼でオレのことを食べようとしてるんじゃないか……って」
震える声で言葉を紡ぐと言うはずのなかったことまで出てきてしまった。
どうしよう、こんなこと言うなんて最低。嫌な気持ちになるに決まってる。今すぐにでも取り消さなきゃ、そう思うのに動揺した口が言うことを聞かない。
「ううん、なるほど?」
瞬きもせずじっとオレを見つめていた咲々牙は勝手に何か納得したようにうなずく。
「そうだね、私はさつきの考えている通り吸血鬼だよ」
「そ、そんな……、うそ……」
「ウソじゃないよ。牙だってあるもの」
そういうと大きく口を開き鋭い犬歯を両手で指差す。
「ぇ、や、やだ。違う。咲々牙は違うよね?お願い、そう言って」
どうして平然といつもみたいにおどけてるの?たしかにいつも冗談は言うけどこんな質の悪いことを言う人じゃないはず。それじゃあ本当に……?
認めたくない事実に力が抜ける。体を支えていた糸が切れたかのようにへなへなと座り込んでしまう。
こわい。眼の前が暗くなったような、そんな感じがして恐ろしい。恐怖から身を守るようにうずくまる。そんなことをして何になるというわけでもないのに。
「待って待って。さつきのこと食べようとしてるとは言ってないってば」
咲々牙が隣に座り込んだような気配がする。
「っ……!やだ、来ないで」
「あのね、私はね、誰の血も吸わなくても大丈夫なんだ。それにね、ヒトを食べることもないんだよ」
拒絶するオレにいつもと変わらぬ調子で語りかける咲々牙。この人の言葉を信じてもいいのか。……わからない。
「……本当に?オレがもっと大きくなってから食べるつもりじゃなくて?」
「本当。食べないよ。食べてしまったらさつきと一緒にいられないもの」
そう言っていつの間にか泣き出していたオレの髪をかき分けて涙を拭う。いつだってそうだ、泣きたくないのに勝手に涙が溢れてる。
冷たい指。熱で寝込んだときになでてくれた母さんの手を思い出すようなひんやりとした心地よさ。その冷たさは吸血鬼の体のせいなのに、そう感じた。
「こわくないよ。私はさつきのことが好きなだけ」
「どうして?オレは咲々牙になにもできないのにどうして?」
「何もできなくても好きだよ」
「……わからない」
「君のお父さんもお母さんもきっとそうだったよ」
「…………うぅん」
「好きってきっとこういうもの」
「そう……、なのかな」
咲々牙はいまいち納得しきらないオレの手を取り立ち上がらせる。そしてそのままぎゅっと抱きしめる。
――前から思っていたけど、咲々牙はスキンシップをとるのが好きだ。オレが不安そうに見えるとすぐに手を握ったり抱きしめたりしてくる。密着するといつもの咲々牙の匂いを感じる。さっきまで恐れていた相手の香りに落ち着いてしまう自分が不思議だった。だけどひんやりした体温に包まれているとゆっくり心が平静を取り戻していく。乱れていた心音が咲々牙とおなじくらいのリズムになっていく。
「私がさつきのことを守ってあげる」
柔らかな声が思考に染み渡っていく。たしかに咲々牙は吸血鬼で、だけどオレを傷つけない?
「…………うん」
「大丈夫。さつきはなにも怖がらなくていいんだよ」
――顔を上げると窓の外の空にはまだ月が輝いている。何も変わらない静かな夜だった。浮かんだ疑念を除いては。