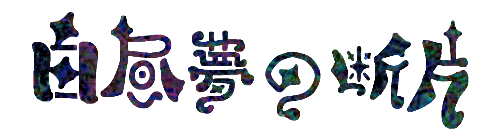あの日から一年。
今ではもう毎日の流れが馴染んでしまった。咲々牙の隣で眠って起きて、地下から上がって夜のうちだけ窓を開けて。自分の身支度を済ませたら咲々牙の体を拭いて、髪を梳かして。花瓶にさす新しい花を庭から摘んで、それぞれの部屋に飾って。その後は本を読んだり、咲々牙のことを想像しながら絵を描いてみたりいろいろ。ほんとうはそこまで空腹じゃないけど、触れる時間が欲しくて少しだけ血をもらったりもする。そうして近くにいると、だんだんさみしさを実感して、抱きついたまま眠ってしまう。そんな繰り返し。
しかしまあ、部屋は綺麗になったしちょっとだけ模様替えもした。咲々牙が見たら驚くだろうか。楽しみだな。
……それと、やっぱりときどき「許して」と寝言を言っているのが気になる。悪夢を見ているのかもしれない。だから毎日一緒に寝るようにしたんだったか。
あの人はまだ眠っている。
あの日から三年。
みつあみはできるようになった。オレの髪だとまっすぐすぎて解けやすいけど咲々牙の髪は柔らかいからやりやすい。せっかくのきれいな髪に癖がつくのもイヤだからすぐに解くようにしてる。……急に目覚めて褒めてくれたり、しないかな。
寝言はだんだん少なくなって、今じゃすっかり静かになってしまった。うなされてないならいいけど、もう声を聞けないのが淋しい。
あの人はまだ眠っている。
あの日から十年。
あの人が本当に生きているのかときどきわからなくなる。けれどそれは心音と食事のときに流れる鮮やかな赤色がなにより証明している。だから血を分けてもらう時間が一番好きだ。体に触れるのも同じく。だけどやっぱり、咲々牙に触ってもらえないのが淋しくて物足りない。あなたなしじゃ満たされない体にしておいてこんな仕打ちはひどいんじゃないかって、目が覚めたら詰めてやるんだからな。
あの人はまだ眠っている。
あの日から五十年
飾った花はすぐに色褪せていく。時間の感覚が不正確になっていく。寝て目が覚めるたびにもう百も二百も過ぎてしまったんじゃないかと錯覚する。だけどカレンダーも星の位置もそんなことはないと告げていて、がっかりする。どのみち咲々牙がいないなら何年経ってても一緒だけど。
あの人はまだ眠っている。
あの日から百年。
花の色も咲々牙から拝借して着ている着物の色も曖昧にわからなくなってしまった。感じるのはあの人の鮮やかな赤色。近頃ときおり訪れる不届き者どもの醜く赤黒いのと対称的にきれいな赤。それを見るたびただ一つだけ生きる意味を感じられた。
もういっそ、あの人は本当は死んでしまっていて、無垢な百合に生まれ変わって会いに来てくれていたら。そうしたら諦められたのに。
あの人はまだ眠っている。
あれから二百年。
ここ最近はすっかり治安が悪くなってしまったのか不届き者の始末をすることが増えた。そのせいで遠出ができない。たまには珍しい花を飾りたくてときどき足を伸ばしていたけど、咲々牙の眠りを守ることがオレの意義。だからせめて庭のものだけで我慢してほしい。何も飾らなくなったらきっと、殺風景なうちを見たらがっかりさせてしまうだろうから。
あの人はまだ眠っている。
あれから三百年。
鏡に映る自分自身の目が真っ赤なことに気がついた。目の色はとっくに赤いけどそういうことじゃなくて、まぶたや目元が赤い。毎日、咲々牙を抱きしめて眠っているうちに泣いてしまうから。だからこうなったんだろうな。責任持ってたくさん甘やかしてもらうからな。子供みたいだって笑われたっていい。こんなに長く留守番したんだからそのくらい許されるに決まってる。
あの人はまだ眠っている。
あれから四百年。
窓の外で流れる星に願っても。髪を切らずに願掛けしても。紙を折って祈りを連ねても。そっと唇に口づけても。咲々牙は目覚めることはない。奇跡なんて存在しないのだろう、おそらく。
あの人はまだ眠っている。
あれから五百年。
どうしてあの人は「ちょっと」なんて曖昧な尺度で約束をしたのだろう。百年、千年、一万年。どれであってもそうやって明確に言ってくれていたら、どれだけよかっただろうか。いつまでと、言ってくれていたならいくらだって待てたのに。いつかそのうちなんて期待を持たせたままなんて、こんなのは呪いと一緒だ。もういっそう、このまま二度と目覚めないと宣言してくれていたほうが楽になれたんじゃないかと、そう思える。そうしたらオレも同じところに行ったのに。
あの人はまだ眠っている。
あれから六百年。
近頃は吸血鬼は忌まわしいものとして討伐の対象であるらしい。不届き者がますます増えてわずらわしい。どれだけ苦しくても咲々牙のことだけ考えていたいのに気が散って邪魔だ。それにあの人が目覚めたときに一緒に出かけられないじゃないか。自分が昔はあんな生き物と同じだったと思うと汚らわしいとまで思える。
どれだけ奴らが集まったとてオレたちの力には到底及ばないのに。いつか咲々牙は言っていた。夜がある限り私たちは永遠だ、と。
少なくとも朝と夜は今も変わらず巡っている。それが忌々しく思えるくらいに。
あの人はまだ眠っている。
あれから七百年。
どれだけ袖を濡らしても涙は枯れることはないらしい。花を飾る瓶を満たせるくらいにはもう泣いたことだろう。これだけオレを悲しませるなんて、やっぱり悪い人だ。信じたオレがばかだった。本当はオレのことなんてどうでもよくて、オレがあきらめた頃に起きてオレのことなんて最初からなかったみたいに別の人を見つけてまた暮らすんじゃないのか。そんなことならいっそ、オレがこの手で殺してしまおうか?オレ以外の誰ももう愛せないように息の根を止めて、そのまま一緒に死んでしまおうか?いつか渡された銀の弾丸で心臓を撃ち抜いて、終わりにしてしまおうか?
……やっぱりだめだ。考えただけで涙がもっと溢れて、拭いすぎて目が痛い。心中するなら最期にあの人の声が聞きたい。オレを愚かで可哀想なままで死なせないで。あなたを疑ったまま殺させないで。ただ一言愛していると、それだけが聞きたい。
あの人はまだ。
あれから八百年。
最近はよく夢を見る。咲々牙といた頃の夢を。もうずっと声なんて聞いてないのに記憶の中と全く同じ声でオレの名前を呼んで、笑って。結ばれるより前でオレから咲々牙のことが好きだって言うときもあるし、咲々牙から家族としてじゃなくて恋人になりたいんだって言われるときもある。あるいは、すでに結ばれた後で互いに愛を囁いてたくさん愛し合う場合もある。いずれにしても一番幸せを感じているときに目が覚めてしまう。夢の中のほうが現実ならよかったのに。咲々牙のようにずっと眠って向こう側に逃げ込んでしまえれば。そうしたら幸せでいられるのに。
それでもまだ、あの人の眠りを守るのをやめられない。夢じゃなくて現実でまたオレを呼んで抱きしめて大丈夫だって、もうどこにも行かないって言ってほしかったから。
あの人は今もまだ。
あの日から九百年。
あの人は、オレと出会うまでどうやって生きてきたのだろう。オレが孤独を感じているより遥かに長く淋しく生きてきたのだろうか?誰かに寄り添ったこともあるようだったけど、どれも覚えていないと言っていた。目覚めたときにはオレのことも忘れてしまっているのだろうか。後悔させないと誓ってくれたことも、愛していたことも全部。……イヤだな。だけど忘れてしまっただけならまた好きになってもらえばいい。咲々牙がそうでなくてもオレは咲々牙を愛しているから。あの人がオレにしたように好きだって伝え続けて、たくさん喜ばせて。そうしたら、もう一度好きになってくれるといいな。
だって、毎日隣にある温度も肌も寝息も、どうしたって嫌いになれないくらいに愛おしいから。もう咲々牙のいない世界なんて考えられない。それは眠ってしまってからも変わらない。あなたの存在だけがオレをただ生かしていた。
あの人はまだ、眠っている。
あの日から九百九十九年。
数十年や数百年に一度しか咲かない花。それらは何度咲いて何度散ったことだろう。
遠くの街の明かりがここからでも見えるようになったのはいつからだろう。
オレがあの人と過ごした時間を待っている時間が上回ったのは何年前からだろう。
そんなこともうどうでもいいのかもしれない。数えることに意味はなくて、むなしさが降り積もるばかり。時間は悲しいくらいにオレを置き去りにした。悲しみさえもいずれは意味を失ってしまうのだろうか。
涙は今なお枯れることがないけど、いつか枯れる日が来ますか。あなたが拭ってくれるまでどれほど泣き続ければいいのですか。
答えて。そう呟いた言葉は闇に消えて、沈黙だけが支配した。
あの人は、眠っている。
あの日から千年。
訪う邪魔者を殺すたびに庭の桜の木の下に埋めていた。積み重ねた屍はもうすでに百を超える頃だろうか。
だからだろうか、今年はひときわ鮮やかでたくさんの花が咲いている。彼らの淀んだ血を啜って薄色と紅色のまだらに美しい花を咲かせて、まるで、あの人のようだ。ずっと昔にもこの花と咲々牙を重ねたことを思い出す。
思わず花を見ながらこぼした言葉にあの人は私はそんなに儚くないと、いなくならないよと、そう言っていたのに。淡い花びらがいつまでも散らずに咲き誇っていればいいのに。
…………小ぶりな蕾を携えた枝を一本だけ手折る。眠っていてもいいからあの人に捧げたい。棺のそばに飾ろう。この枝の花が咲いて散るまでに。……決めないと。あの人もずっと苦しんでいるだろうから。
ひどく懐かしい暖かな季節の匂いがまたオレの頬を濡らしていた。