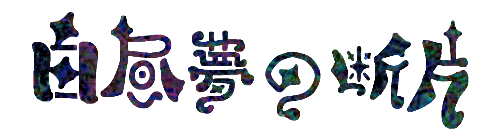窓の外の景色からは色彩が失われ、風が吹くたび枯れ木が淋しく枝を揺らしていた。
この季節はどうにも好きになれない。四季の彩りを感じるようになったのはあの子と暮らし始めてからだけれども。
それでもやはり過ぎゆく時間に焦燥を感じて、落ち着かなくなってしまう。
あの日、続きは大人になってからと約束してからどれだけ朝と夜が過ぎただろう。あまり年月というものを意識しないからあいまいだけれど、さつきが私の身長を追い越すくらいの時間が経ったことだけは確か。
あれからもさつきが許してくれる範囲で日々いたずらを続けて、それでも相変わらず恥ずかしがるあの子が可愛らしくて。さつきと同じ時間を過ごすほどにずっと一緒にいたい気持ちは強まっていった。
ずっと一緒にいられる方法。それを私は知っている。
……あの子の時を止めてしまうのならば、肉体の最盛期が望ましい。
すっかり背も伸びて、日々触れる体もしっかりしてきたこの頃。今がそのときなように思える。
熟れすぎた果実は収穫のときを過ぎれば地面に落ちてしまう。そうなる前に正しく刈り取らなくちゃ。
覚悟を決めて、机に向かって何か描き物をしているさつきに声をかける。
「あのね、大事な話があるんだ」
「わっ……!? いきなり後ろから、びっくりするだろ……!」
随分集中していたのか私の気配に気づかなかったみたい。描いていた用紙を慌てて裏返して隠すさつき。これも気になるけど今は話をするのが先。
「それでなに……?」
「あのね、私はさつきのことが好きでね、ずっと一緒に居たいと思っているんだ」
「うん」
「……さつきも私とずっと居たい?」
「なんか、……居なくなっちゃうかもしれないみたいな言い方するなよ」
「わたしにとってはそうなんだよ」
真剣な様子を察したさつきは椅子をこちらに向けてまっすぐに私を見ていた。
「いつかはね、さつきは私より先にいってしまうから」
「…………」
「だから、私とずっと同じ時間を生きて欲しい。……さつきが嫌じゃなければ」
その言葉にこれまで真面目な顔をしていたさつきが笑いをこぼす。
何かおかしいことを言ってしまったかな。
「それ、『嫌じゃなければ』はずるいって前にもいっただろ」
「あっ……! ごめんね」
しまった。口元を袖で覆い隠し他の言い方を思案するも代わりの言葉は出てこない。
言葉を続けられずにいるとさつきは立ち上がり私のことを抱き寄せる。背中を撫でられている? あたたかい。
「嫌なはずない。できることならずっとさつきといたい」
「私が、言うから無理をしていない?」
「してない。だから、そんな泣きそうな声をしないで」
私、そんな泣きそうにしていた? やっぱり自分じゃわからないや。
「私の我儘に無理に付き合わないでいいんだよ。大事なことだから、ね」
「オレは自分の意志で咲々牙と一緒にいたいと思ってる」
全く迷いのない返事。背に回されていた腕は解かれて、私を正面から真っ直ぐ見つめていた。
「……いいの?」
彼はこくりとうなずく。
「それで、……そうする方法があると?」
「あるよ」
「だろうな、そうでもなければこんなこといきなり言い出さないよな……」
「だって、今こうしている間にも少しずつ別れのときが近づいてきているんだもの」
「そんなにすぐオレは居なくならないって」
私をなだめるようにさつきは頭を撫でる。もう、私より大きくなったからって。
「私にとってはすぐなんだよ?」
「わかったからそんなむくれるなよ」
私の様子に笑い声を漏らす。本気で言ってるんだけどなあ。でもさつきが笑っているならいいか。
「それで、オレはどうしたらいい?」
「さつきがね、私の眷属になってくれたらずっと居られると思うんだ」
「けんぞく?」
「私の血を分けて、同じ吸血鬼になるんだよ」
「吸血鬼……」
話を聞いたさつきは顎に手を当て何か考えている様子立った。
「やっぱり嫌、かな……?」
「そうじゃなくて……! あの、咲々牙は一度もオレの血を吸ってないだろ」
「うん……?」
「だから、その、こんなこと言うのも変なんだけど……、オレがヒトのうちに、」
彼が言葉を紡ぐのを待つ。
「食べてほしい……」
「えっと、もしかしてえっちな話?」
「ば、ばか……! そうじゃなくて……」
「冗談だよ?」
「もう……!」
「私はさつきを傷つけないって昔約束したよね。なのに血、吸ってもいいの?」
「オレはイヤじゃないから……! それによくわからないけど、ヒトの血のほうがきっといいんだろ?」
「うーん、そうかな……、そうかも」
なにしろ私は姉妹と違って眷属を作ったことがないから。姉妹の血を啜ったこともないから同族の味は知らない。……味、違うのかな?
「いいの? 噛まれると痛いよ」
「……やさしくして」
「えっと、今……するの?」
「……ん」
そのままだとやりにくいと思ったのか、さつきは私とお揃いの首元まであるインナーを脱ぎ始める。
露わになった肌は色白で、だけど不健康さを感じないしっかりとした体つきで。特別に筋肉質というわけではなく柔軟さのある触り心地。ときどき触っているから知っている。
「綺麗だね」
「そ、そんなことな、っ……!」
空気に晒されて少しだけひんやりしたお腹から上へと指先で体をなぞる。
こそばゆい感覚にびくりとするも、どうにか我慢している様子が可愛い。
「誰よりも、何よりも綺麗だよさつき」
「その、恥ずかしいから……! するなら、は、早くして」
「待ちきれないの? さつきのえっち」
這わせた指で首筋を撫でる。傷一つないそこに今から私が傷をつけることを思うと恍惚と罪悪感で頭がぼんやりとする。
「本当にいいの?」
「いいからっ……、……痛くしてもいいから」
あまり焦らすのも可哀想なのでそろそろいただこうかな。
緊張して体をこわばらせたさつきを抱き寄せる。こするのも何度目だろう。数え切れないほどこの子を抱きしめてきたけれど、今が一番ドキドキしてる。私もさつきも。
「いただきます」
白い首筋に口づけ。そうしてそのまま牙を食い込ませる。
「ん、…………っ!」
痛かったのかな、ごめんね。なんて、言葉をかけにように口がふさがっている。薄い皮膚から流れ出る血を零さず啜らなければ。一滴も無駄にしたりしない。
温かい雫は美味しい美味しくないの次元でなく、ただただ彼の生があることを強く感じさせた。それを貪ることを許されている事実が私を恍惚に誘う。
ああ、大好きな私のさつき。ずっとずっと、離したくない。このまま今が永遠になればいいのに。どこにも行かず私だけのさつきでいて欲しい。私の全てをあげるから、さつきの全部が欲しい。どうか、離れずにずっとそばにいて。
さつきの首にかぶりついてどれだけ経っただろう。刹那が永遠に思えるような陶酔の中で、髪を撫でられていることに気づく。
「さつき?」
「なんだか、ちいさな子供みたいだったな」
「もう、さつきだってそうなるよ。きっと」
「かもな」
傷口の血はすでに止まっていた。その傷までも愛おしくて、口づけを落とす。
「……痛かった?」
「少しだけ、……それよりもちょっとだけ気持ちよくてふわふわした」
痛いのに気持ちいいなんて変な感じ。でもさつきが嫌じゃないならそれでいい。……次は私にもして欲しいな。
「具合は大丈夫? くらくらしたりしない?」
「平気だよ」
そうは言うものの脱力した様子に見える。恍惚感が抜けて私もちょっと疲れてしまった。
ぼんやりしたさつきをいわゆるお姫様抱っこで持ち上げた。多少私より大きくなったとて、このくらいは造作もない。
「〜〜〜っ! ちょ、ちょっと!?」
「昔よりも重たくなったね」
「重たくなったじゃなくて、え、なに、降ろして……! 自分で動けるからっ……!」
混乱しながらも暴れずにしっかり私にしがみつくので運びやすい。そのままベッドに降ろして、その隣に倒れ込む。
「な、なんでいきなりこんな……」
「うーん、今くらいじゃないとできなさそうだったから?」
よっぽど油断してないと拒否されてしまうもの。
「怒った?」
「そんなことで怒らないってば」
「ふふ、知ってる」
横にいるさつきの手に自身の指を絡める。すると無言で握り返してくれる。そんな自然な動作も愛おしい。
「三日後は新月だから」
「うん?」
「だから儀式はその日にしよう」
「ああ、うん……」
はじめは何の話かわかっていないようだったさつきはすぐに意味を理解する。
今のさつきを見ていられるのもあと少し。そう考えると今のうちにもっと堪能しておきたい気持ちになってきた。
「さつき」
「ん」
「好きだよ」
昔よりもたくましい腕に抱きついて肩に顔を埋める。私の大好きな匂い。息を深く吸って吐いて、私の中がさつきで満たされていくみたいで気持ちがいい。
「……オレも、すき」
小さな声で返事が聞こえた。いつもは恥ずかしいからって、滅多に応えてくれないのに珍しい。
「大丈夫、全てうまくいくよ。だから今はおやすみ」
「ん」
さつきも私の方へと身を寄せる。このまま二人で眠ってしまうのにさして時間はかからなかった。
それから一日、二日、そして三日。いつもならあっという間に過ぎるのにすごくじれったく感じた。いつもより多めにさつきに触っても大丈夫だったのはよかったけれど。
すっかり日が暮れて、窓枠に黒い絵画が飾られる頃。どことなく落ち着かない様子のさつきに声をかける。
「そろそろだよ」
「う、うん」
「地下室に行こうね」
さつきの手を取り家の地下へ。ほとんど使うこともないから埃っぽい。
「足元気をつけてね」
一度、手を離して明かりを灯す。それでもやはり薄暗い。私の目にはしっかり見えるけれど。
地下室には私の棺と使うことのあまりないものの収納がいくつか。それと石造りの祭壇。
うろ覚えの記憶を頼りに必要なものを引っ張り出す。本当は道具なんてなんだっていいんだけどこういうのは雰囲気が大事だもの。
黒い衣装と黒いレースのヴェール、ええとそれと。黄金の杯とオニキスのナイフ。他にもあった気もするけどこれだけあれば事足りる。
「おまたせ。はい、これ」
「着替えればいいのか?」
「うん、お願いね」
さつきに衣装を渡して着替えてもらっている間にこちらの準備をする。
祭壇に燭台を置いて火を灯す。黒い刃を手首に走らせて、流れる血を杯に注ぐ。ひたひたと、黄金を鮮やかな赤が満たしていく。
このくらい溜まれば十分かな。私も着替えないとね。
「ちゃんと着れた?」
「た、たぶん?」
「どれどれ」
着崩れていた部分を簡単に直してヴェールもかぶせる。鏡には真っ黒な衣装を纏った私達が映っていた。
「うん、これでばっちり」
「あの、オレ、どうしたらいいのか全然わからないんだけど……!」
「私の言うことに雰囲気で答えてくれれば大丈夫だよ」
「簡単そうに難しいこと言う……」
「要するに誓いを成立させればいいんだよ、できるよ」
「うん……」
まだ不安げなさつき。こういう私も初めてなんだけれど。
「そろそろ始めようか」
祭壇の前に向かい合って立つ。決まりきった聖句のように自然と言葉が出てくる。
「これより汝を我が眷属とする儀を執り行う」
「古の盟約に依り我が血を汝に分け与え、永久の伴侶とす」
「汝、其れを望むか?」
「……はい」
「我が伴侶に永久の祝福を」
ヴェールを上げて口づけを。さつきの驚いた顔が可愛らしくてつい顔が緩みそうになるけれど、我慢して続ける。
杯を掲げて、祈りを捧ぐ。
「大いなる夜の父よ、我らが誓い見届け給え」
「これより汝に小夜啼の名を与える」
「小夜啼 鎖月、我と共にあれ」
私の血で満たした杯をさつきに渡す。戸惑っていたが意を決してそれを飲み干す。
「これでおしまいだよ」
「あ、ああ」
答えた直後、さつきは倒れ込む。もちろん倒れるより先に受け止める。
「大丈夫、すぐに馴染むよ」