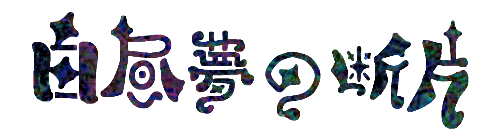異変を感じたのは、杯に注がれたあの人の血を飲み干してすぐのことだった。
全身が焼けるように熱い。薄暗いはずの地下も燭台の光が異常に眩しくて、湿った匂いがやたら強く感じられた。体の感覚全部がうるさくて、気持ちが悪い。
立っていられない。大丈夫だと、そう言って蝋燭を吹き消した咲々牙を見たのを最後に意識が途切れた。
目が覚めると寝室のベッドの上にいた。窓の外は暗い。なのに部屋の明かりなしでもよく見えた。
ベッドの横の椅子で居眠りをしていたような咲々牙は目を開けるなりオレに抱きついてくる。
「おはよう、鎖月。気分はどう?大丈夫?変な感じ?落ち着かない?」
矢継ぎ早に質問を投げかけてくる。よっぽど心配だったのか。
「感覚全部が鋭くなったみたいで、ちょっと落ち着かない」
「そっか、でもきっとすぐ慣れるよ」
その声は心どこかうれしそうで、オレが目覚めるのをずっと待っていたような気がした。
……抱きしめられていると前よりも強く咲々牙の匂いを感じる。
春に咲く、淡い花のような香り。綺麗なのにすぐに散ってしまう儚い花。オレの中の咲々牙の印象と一緒だ。ふわりとしていて自由なのに、だけど急にいなくなってしまいそうで不安になる。
だから咲々牙を捕まえていられるように強く抱きしめ返した。
「ふふ、鎖月とこうするの昔からずっと好きだよ」
いたずらっぽく笑うその声がオレは好きなんだけど。そう口に出すのはなんだか恥ずかしくて心の中でだけつぶやいた。
……ふと気になったことを思い出したので聞いてみる。
「あのさ、儀式のとき、伴侶って」
「うん?」
「オレを伴侶にって、言ってなかった……?」
「言ったね」
「それは形式上とかで……?」
「ううん、違うよ」
「じゃあ、どういう、」
「もう、鈍感なんだから。わかるでしょう? 婚礼の儀なんだよ、あれは」
オレを吸血鬼にするとは聞いたけど婚礼とは聞いてない。聞いていたとしても、拒否するつもりはなかったが。
「オレと咲々牙は、その、そういう、……ってこと……?」
「そう、鎖月は私のお嫁さん」
「女じゃないのに……」
「私は鎖月が男でも女でも好きだよ」
それはこっちだって一緒だ。意識してすぐはちょっと頭が混乱したけど、今はどちらであっても変わらずに好きだって確信できる。
「オレも。咲々牙が何であっても好き、だ」
抱き合っていた体を一度離して向き合う。そして今度はこちらから唇を合わせた。
……やわらかい。不思議な感触に浸っていると咲々牙が閉じた唇に舌を差し込んでくる。
なすがままにしていたら口の中を探るように蹂躙される。中でも犬歯を執拗になぶられている感じがする。……見えないから確かなことは言えないが。
呼吸をするのを忘れていたのか酸素が足りなくなってきた頃、咲々牙のほうから口を離される。なんだか名残惜しい気がした。
「歯、尖ったね」
「……?」
それはいったい……? 犬歯は他の歯より尖っているものだからいまさら言うまでもないんじゃ。
オレが疑問符を浮かべているとあの人は立ち上がり手鏡を持ってくる。
そしてそれをオレに手渡す。
「え?」
鏡に映っていたのはオレじゃない。真っ白な髪にそれと同じ色の睫毛、そして白目部分は黒くて真っ赤な瞳の、……誰?
「口、開けて見てごらん」
言われたとおりに口を開ける。すると鏡の中の誰かも同じく口を開く。少なくともこの見覚えのない人物はオレであるらしい。
オレの歯は、咲々牙と同じように鋭く尖っていた。皮膚を突き刺して生き血をすするための道具としてのもの。それをオレは知っている。
それにしても、どうして。こんなふうになってしまったんだ?
「あの、なんで、こんなふうに……」
「うーん、……私の眷属になったから?」
あの人もそんなによくわかっていないみたいだ。たしかに眷属を作るのは初めてだと言っていた。……初めてなのはちょっとうれしいけど。
鏡をもう一度覗き込む。元の自分とは似ても似つかない人物が映るのはなんとも気味が悪い。
それに、今まで咲々牙が好きだと言ってくれた黒い髪も黒い目も別物になってしまった。どうしよう、これで嫌われてしまったら。嫌いとまで行かずとも前のほうがよかったと思われたら。
不安はあっという間に心に染み渡る。こんな姿で咲々牙と顔を合わせるのが怖い。
「ちょっとしばらく、一人にさせて」
「えっ、鎖月、どこ行くの……!」
引き止められる先に自分の部屋に逃げ帰り鍵をかける。ドアの向こうでオレを呼ぶ声がするけど、答えられない。明かりもつけずに暗闇の中ベッドに座り込む。
これからどうしよう。せっかく、咲々牙と……。
考えるほど落ち込む。思考が嫌な想像の渦に飲み込まれていく。
視界に映る自分の髪の白が疎ましい。
……いつの間にこんなに髪が伸びたんだ?
てっきりあの日に倒れてからせいぜい数日程度だと思っていたけど、そうじゃないのかもしれない。あの人はカレンダーを貼り替えたりしないから部屋の様子を見たところでわからない。
……もしオレが思ったいたより長い時間が経ってたとしたら。そうしたらずっとあの人を一人にしてしまったんじゃないか。あの人を悲しませた挙げ句、オレは元のオレじゃなくて。きっとガッカリさせてしまった。
視界が滲む。気がつけば、目元から頬に生温い液体がこぼれていた。咲々牙に子供っぽいと思われてしまうのがイヤで泣かないようにしていたのに。だけど今は見られているわけじゃない。それなら関係ないか。自分で考えていて悲しくなる。咲々牙とオレが関係ないって、いやだ。
涙は止めどなく溢れてくる。そのたびに何度も拭って、目が痛い。
それでも、自分が泣いているという事実すら鬱陶しくて。……笑われてもいいからあの人に涙を拭ってほしかった。でもこんな姿じゃ咲々牙に合わせる顔がない。だけど今すぐ抱きしめてほしい。噛み合わない願望と現実に動けなくなる。
「鎖月」
ドアの向こうからまた声がした。その声がオレの意識を引き戻す。呼びかけが続くことはなかったが代わりにドアの下の隙間からなにか差し込まれた。
……手紙?
その紙を拾い上げて見てみれば綺麗な字で言葉がつづられていた。
『親愛なる鎖月へ
うまくいってよかった。これからずっとキミと同じ時間を生きられることが何よりも嬉しい。
私はいつも伝えているつもりだったけれど、上手に伝えられていたかわからないからここでもう一度伝えさせてね。
私はキミを、鎖月を初めて見たときからずっと愛している。外見だけじゃなくてもっと、魂のような深いところからキミしかいないと思った。家族、友人、恋人、キミの全てになりたかった。私の与えられるもの全て与えたかった。初めはそれだけでよかったのにいつの間にかキミのことがもっと欲しくて。キミをこうしたのも本当は私の我儘だってわかってる。私のエゴでキミを変えてしまってごめんなさい。
だけどそれでもキミを愛している。どうか私のそばにいて欲しい。
キミをこうした責任を取るから。鎖月を幸せにするから、どうかお願い。
小夜啼 咲々牙』
不思議と暗闇の中でも字がよく見えた。
ああ、俺に与えた名って、こういうことだったのか。文字で見て初めて意図を理解した。
……便箋の最後の方は字が滲んでいた。
こんなことされたら無視できないじゃないか。意を決して扉を開ける。
「鎖月!」
ぶつかるくらいの勢いで咲々牙が胸に飛び込んでくる。しんみりした手紙の雰囲気が嘘みたいだ。
「あ、危ないだろ……!」
「ごめんね。……読んでくれた?」
「……ん」
オレにはわかる、いつもと変わらない風を装いながら少しだけ不安げな声をしてる。
ぴったりとくっついた咲々牙を一度引き剥がして向き合う。
「……約束して。オレを後悔させないって約束して」
「うん」
「かみさまや他の誰でもなく、オレに誓って」
「鎖月のこと、誰より幸せにして後悔させないって約束するよ」
昔は恐ろしくも思えた咲々牙の目。今なら直視できる。
揺らぐことなく真っ直ぐにオレを見据えた赤い瞳はその言葉に嘘偽りがないことをなによりも確かに示していた。
「あのね、鎖月の目はね、私とおそろいなんだよ」
言われてから気づく。鏡で見た赤い目はこの人と同じ針のような鋭い瞳孔に鮮やかな赤色をしていたと。
「それとね、見て!」
咲々牙は暗がりからオレを連れ出すと自身の前髪を指差した。
それは夜の空のような漆黒から部分的に白く染め上げられていた。
「鎖月とおそろいにしたんだ」
「……似合ってる」
「ふふ。ね、これで少しは嫌じゃなくなった?」
「かもな」
ああこの人は、いったいどこまで可愛いんだろう。昔からオレを元気づけたり喜ばせようとしたりするところ、好きだったな。もちろん今も好きだけど。
「ねえ、鎖月お腹すいてない?」
言われてみるとそんな気がする。あのときからずっと何も口にしてなかったはずだ。
「私をお食べ」
「なんかやらしく聞こえる」
「鎖月がそうしたいならそれでもいいよ」
冗談のつもりが真顔で返されてしまった。逆に反応に困る。
「ほら、おいで」
咲々牙はインナーの首元を下にずらして誘うような仕草を見せる。
……いつかオレがされたときみたいな気分に咲々牙もなるのだろうか。そんな咲々牙を見てみたい。欲望が首をもたげる。
「…………」
あの人の手を引いて再び暗がりへ。そのままベッドへ押し倒す。
「ずいぶん積極的だね」
「う、うるさい……!」
咲々牙が身につけている黒いインナーを脱がせる。すると真っ白な肌が露わになる。女性的な膨らみはないが男性としても華奢な体。薄紅色の胸の小さな突起が白の中で目を惹く。
「鎖月に触れられたい、な」
ねだるような声色が理性を奪う。これはどう考えても”そういう”ことを求められている。
とはいえ、どう触れたらいいのかなんて知らない。
だからといって今さらやめるなんて選択肢はないので、これまで咲々牙にされてきたのを思い出しながら体に触れる。
腹から上へ指先を滑らす。そして胸のあたりをなでる。そうしていると突起は少しばかり膨らみを増したように感じる。
咲々牙の顔を見てみるとこれまで見たことのないような恍惚とした表情を浮かべていた。
「……やめないで」
目が合うと切なく吐息を漏らしながら言われてしまった。
期待に答えられるように続けることにする。
薄紅の膨らみを優しく弾くと体を震わせ甘い声を上げる。
「ぁ、あ、さつきっ……!」
「……痛かった?」
「もっとして、おねがい」
悦びの反応なのは言わずともわかる。懇願する声が聞きたくてこんな確認をしたのかもしれない。そんなことはどうでもいい。理由なんていらない。今はただ、咲々牙に溺れていたい。
胸の突起は触れるほどに硬さを増す。それに合わせてこちらも優しくからつまみ上げるように嬲る。またがった体の下腹部の感触が咲々牙が気持ちよくなってることを伝えてくる。
「ん、ぁあ、さつき、すき。それ、すきっ……!」
そんな声で名前を呼ばれたらもう、正常な判断力はとけて消えてしまう。
湧き上がる衝動に身を任せて首筋に顔を寄せる。そしてそのままそこに噛みつく。咲々牙の体にに傷をつける背徳感さえ興奮の材料にしかならなかった。
血をすすりながらも胸をもてあそぶ手は止めない。
「あ、っあ、さつきっ……! さつき、さつき……! ゃあっ、ああっ」
咲々牙の血はこれまで口にしたどんな食物よりもおいしく感じられた。愛しい人に呼ばれる声も感じる香りも触れ合う感触もすべてが気持ちよくてどうにかなってしまいそうだ。
「さつき、さつきっ、さつき、好き、すき、……ッあ、ぁ、〜〜〜!」
声にならない悲鳴と同時に体を震わせてオレの背中にしがみつく。
……反応からするに、達してしまったようだ。
思っていたよりもつけた傷は浅くて、血は止まっていたので口を離して咲々牙の顔を見つめる。
頬を紅潮させて瞳を潤ませていた。こんな咲々牙は見たことない。オレの興奮は覚めるどころか昂りを増すばかりだ。
「さつき、このまましよ……?」
軽く呼吸を整えた咲々牙は自ら残っていた衣類を脱ぎ捨てる。
本当にもう、理性の限界だった。
そこから先のことはよく覚えていない。咲々牙に導かれるままに体を重ねて、互いの体の境界もわからなくなって。右も左も上も下もわからず、互いが存在してる以外は全部不確かで、とろけるような快感で混ざり合って。
そうやって何もわからなくなったまま、いつの間にか意識を手放していた。
朝、目を覚ませば隣には愛しい人。なんて、感慨に浸るよりも先に朝日が異常に眩しい。これまではなんてことなかったのに、レースのカーテン越しの光が視界への暴力みたいに明るい。
「おはよう、さつき」
伸びをするとむくりと起き上がりぴしゃりとカーテンを閉める咲々牙。
「眩しかったよね? しばらくすればもうちょっと慣れるよ」
「それはいいけど、その、服着て……」
真っ白な肌はシラフで見るにはあまりに刺激的で。見たくないわけじゃなくて、目のやり場に困ってしまうから。
「昨日はあんなに積極的だったのに?」
「今は別……!」
「それなら今度は私が鎖月のこといじめてしまおうかな」
「わっ……!?」
昨日とは逆の体勢。首元に垂れる咲々牙の柔らかな髪がくすぐったい。
「もう、なに笑ってるのー?」
「髪の毛くすぐったくて……」
わざとすねたような声をする咲々牙。……可愛い。
この人はオレよりずっと生きてていつも飄々としているように見えるのに、ときどきこうやって子供っぽいところがある。そんなところが放っておけないように思えて。だからつい頭をなでてしまう。
「私の身長を追い越してからずいぶん大人になった気でいるみたいだね」
「咲々牙が子供扱いしすぎなだけだ」
トゲのある発言をしながらも髪をとかれる顔は心地よさそうで、見惚れるほど美しい顔立ちだった。
咲々牙の目はあまり見つめると心が読まれてしまいそうでこれまでよく見れなかったけど、今は不思議と平気だった。
おっとりした印象を覚えるたれ目に長いまつげ。眩しいから、と片目を覆った前髪はまばたきのたびに小さく揺れる。
邪魔そうに見えていたけど今ならそのまぶしさがわかる。咲々牙の感覚が少しでも共有できることがうれしい。
「私の顔、なにか変だった?」
「いいや。……ああでも、前はしてたお化粧、もうしてないんだな」
咲々牙をじっくり見ていてなんとなく思い出した。昔は黒や紫の、そういうのを塗っていたような……?
「ずいぶん前だね。黒は子供受けが悪いと思ってしばらくしてないなあ」
「似合ってたのに。……それにもう子供じゃないって言ってるだろ」
「本当? 鎖月がそう言ってくれるならまたしようかな」
すっかり上機嫌になった咲々牙は柔らかく微笑む。どんな顔をしていても綺麗だけどやっぱり笑ってるのか一番好きだ。
「鎖月としたいこと、たくさんあったのにいざやろうと思うと出てこなくなっちゃうなあ」
「……たしかに」
オレも咲々牙としたかったことが色々あった気がするのに、ただ一緒にいるだけで満足してしまう。
前はずっとはいられないから、何かをしていないともったいないような気がしていたのかもしれない。
幸せの青い鳥はずっと、そばにいたって。そんな物語をなんとなく思い出す。
「でも一つは達成できたよ」
「……?」
「ずっとおあずけにしてた、鎖月の思う『えっちなこと』できたもの」
「っ〜! 恥ずかしいからわざわざ言うなよ……!」
言われると昨日のことを思い出して体が火照ってしまうから。その熱は触れ合った素肌には隠せずにバレてしまうだろう。
「ふふ、顔赤い。やっぱり鎖月は可愛いよ」
「可愛いのは咲々牙のほうだろ……」
聞こえないくらいに小さくつぶやく。でもそれは耳に届いてしまったみたいで、咲々牙は目を瞬かせて驚いたような顔をする。
「私、可愛いのかな?」
「…………誰よりも可愛い」
「そう言われたのは初めてかもしれないなあ」
咲々牙の初めてになれるのがうれしい反面、大体のことは初めてじゃないんだろうなと思うと妬ましくなってしまう。オレの初めてのことばかり奪って自分のはくれないなんて少しずるいと思う。
そんなことを考えるオレを知ってか知らずか、咲々牙は手指を合わせて絡め合ってくる。
……指を触れ合わせているだけなのにどことなくいやらしい感じがする。
「これからは毎日一緒に寝てくれる?」
「毎日いたずらしてくるつもりだろ」
「だめなの?」
「……だめじゃない」
「じゃあいいでしょう?」
「仕方ないなあ」
本当はうれしいけど素直に言うのはちょっと照れくさい。毎日そういうのをするのも。
「あとは、一緒にお風呂も入ろうね」
「そ、それはちょっと……!」
「全身見られてるのにお風呂はだめ……?」
「普段のとき見られるのはまた別だから……!」
「そんなあ。だって、髪の毛洗うの大変だよ?」
「自分でできるってば! ……どうせお風呂でもやらしいことする気だろ」
「ううん、するかしないかで言ったらするかも」
「まったくもう……!」
毎日そんな調子じゃこっちの体がもちそうにない。でもやっぱり咲々牙に触られるのは好きで、またわけもわからないくらい交わってどうにかなってしまってもいいと思えている自分もいる。
「鎖月は触られるの嫌?」
「イヤならあんなこと、しないだろ……」
「それならこれからもたくさん触っていい?」
「……そのぶん咲々牙のことも触るからな」
「ふふ、いいよ」
一瞬だけ不安げに揺らいだ瞳。オレの返事でそんな様子は影も形もなかったように消え去る。
そしてオレの首元にぽふりと顔を埋める。やっぱりいい匂いがする。
……密着するのは好きだけど顔が見えなくなることだけが難点だな。
「さつき」
「……ん」
答えると首筋にあたたかな感触と唇の触れる柔らかさ。こそばゆさが妙に気持ちよくて、そこから先をつい期待してしまう。
「あの、咲々牙はお腹空いてない……?」
「まだいいよ。……それに今したら鎖月のこと、抱きたくなってしまうもの」
さらりととんでもないことを言ってくれる。が、あえてそれには触れないでおく。
「ね、夜になったら外へ行こうよ」
「いいけど何しに……?」
「……うーん、ふらふらしに?」
「はは、何それ。でも悪くない、な」
咲々牙と一緒ならどこでもいい。人の道を外れたって、地獄に落ちたって構わない。この人といられることが1番大事だから。
閉じたカーテンの隙間からわずかに漏れる光は陰りを見せることなく眩しくて、やっぱり目をつむってしまう。
だけどそれも咲々牙の言うとおりいずれ慣れるのだろう。色々なことが変わってしまったけどきっと時間が解決してくれる。
時間はいくらでもあるのだから。