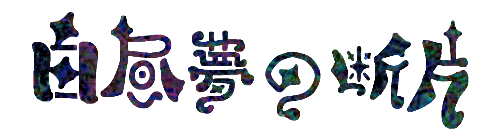ちいさな白い花が咲き乱れる中に私と鎖月二人だけ。風が吹けばその葉がザアとさんざめいて私たちの髪を揺らす。
いつしか花は星の明かりを受けて淡く光りを灯して、小さな光と花弁が風に舞う。そんな幻想的な景色に言葉を失くして二人でただ立ち尽くしていた。
あの子が私の血を受け入れてくれてから毎日が幸せだった。
しばらくはひたすら互いを貪り合って色に溺れたりもしたけれど、それも悪くなかった。朝も夜も忘れて、互いの境目を失うくらいに混ざり合って。そうしていると元から一つに結ばれた存在だったような気さえして。
鎖月の体はどこまでも甘美で、きっと鎖月にとっての私もそうだったから。だからごく自然なことだった。
だけどそれも、鋭敏になった感覚が馴染むのと一緒に衝動の抑えも効くようになって落ち着いていった。……全くしなくなったわけではないけれど。
とにかく、そうして私と鎖月は永遠に結ばれた。
だから今日もこうして真夜中のお散歩中。
私がぼんやりとそんなことを考えていると、鎖月が花を一輪摘み取って私に差し出してくる。ちいさな光は少しずつ零れ落ちていく。
「私に? ありがとう」
「帰るまでそのままだといいんだけどな」
「ふふ、ただの花になっても綺麗だよ」
受け取った花を眺める。私の目にも眩しく映らないような儚い光。両の手で包みこめば隙間から光が溢れる。
こんなに美しいのにきっと夜明けを待たずに失せてしまうのだろう。
ふと、いつか聞いたおとぎ話を思い出した。
「ね、鎖月。願いを叶える想い出の星の話、知ってる?」
「昔聞いたことがある、な」
「これもその一つなのかもしれないね」
星の光を浴びて輝く花々を見ているとそんなふうな気がした。
「鎖月は何かお願いしたいことはあるかい?」
「…………ない、と思う」
「私もだよ。もう全部叶えてしまったもの」
ずっと一緒にいられますように、なんて願わなくてももう大丈夫だから。
「……帰ろうか、せっかく摘んでくれた花が萎れてしまうよ」
「ん」
夢のような景色にどこか浮ついた気持ちで言葉少なに二人並んで歩く。
鎖月も願いはないと言っていたけれど、本当にそうなのかな。……あのとき、彼にわずかに迷いがあったのを私は見落とさなかった。
もしそれが、……「かえして」だったら。
昔は考えもしなかったけれど私が鎖月から奪ってしまったものはたくさんある。あの子の両親、日の光を浴びられる体、自由な暮らし、交友関係、自然な五感、貞操、ヒトとしての人生。挙げればきりがない。
それだけじゃない。私の血が混じってから少しずつだけれど変わってしまったように思えるところがある。
いつだったか、夜歩きの最中遭遇した質の悪い輩を迷うことなく細切れにして返り血に濡れながら私に微笑みかけた鎖月。
その姿は背筋が凍るほど美しくて、なのに悲しく思えてしまった。教えずとも力を上手に使えたことを褒めるべきなのだろうけれど、そんな気持ちにはなれなかった。
だって、前は虫すら殺せないほど心優しかったあの子がこんな、一切の躊躇なく他人を殺めるなんて。
それ以降も夜歩きでヒトに出会う度に鎖月はそれらを”消して”しまった。ときには敵意を感じないものまで。
私にとってはそれはありふれたことだったけれど、なのにあの子がすると違和を覚えて。
だからなぜなのか問うてみた。そうしたら、「……邪魔だった」と、そう言っていた。自分と咲々牙だけの時間に入ってこないでほしいと、疎ましそうにこちらを見る目が嫌だったのだと。だから殺したと告げるその表情は眉一つ動かすことなく、ごく普通のことをしたまでだというみたいで。
私の冷たい血が入ったから。優しいあの子を私の血が毒してしまった。私の身勝手な願いのせいで。
ああ、どうしよう。私は取り返しのつかないことを。前はこんなことなかったのに。罪の意識なんてなかったのに。いつから気づいてしまったのだろう。
きっと、あの子の血が、優しくて温かい血が私の中に入ったから。だからヒトの心を得てしまったのでしょうか。
どうか、許して欲しい。そんなことばかり考えているとすでに私たちは玄関の前にいた。
なかなか扉を開けようとしない私の肩を鎖月がつつく。
「……鍵、忘れた?」
「ごめんね、ぼんやりしてただけ。大丈夫だよ」
「よかった。……壊して入ったら直すの大変だからな」
冗談めかして笑う姿に安堵を覚える。ずっとこうだったらいいのにな。
家に入って花瓶を用意しようとして気づく。
手にしていた花はすでに光をなくして萎れかけていた。